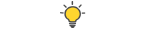1月10日の「今日は何の日?」は「110番の日」です。
また「110番の日」にちなんで「交番の名前の由来」「なぜ110番という番号なのか」など警察にまつわる面白い雑学を紹介します。
1月10日は110番の日
今回は「110番の日」について解説していきます!
なぜ1月10日が「110番の日」なのかというと、「1」と「10」という日付を合わせると「110番」という番号になることが由来となっています。
警察庁が1985年12月に制定されて、翌年の1986年から実施されている記念日となります。
110番はGHQの勧告によって1948(昭和23)年10月1日に、東京等の8大都市で始められたものでした。
東京では最初から110番という番号になっていましたが、大阪・京都・神戸では1110番、名古屋では118番等地域によって番号が異なっていました。
現在では全国共通であることが当たり前になっているため、地域によって番号が違ったのはとても意外ですよね。
全国で110番に統一されたのは1954(昭和29)年のことでした。
毎年の1月10日の「110番の日」には、全国の警察でダイヤル110番の有効・適切な利用を呼びかけるキャンペーンなどが開催されています。
110番の利用率は昔に比べて格段に上がったとされています。
昔は110番をするのにも公衆電話からかけなければいけない時代でしたが、携帯電話が普及しやすくなった事から一気に110番への通報が増えたのです。
現在は全国で3~4秒に1回のペースで110番が利用されています。
警察の雑学
今回は「110番の日」にちなんで「交番の名前の由来」「なぜ110番という番号なのか」など警察にまつわる面白い雑学を紹介します。