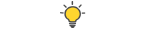4月19日の「今日は何の日?」は「地図の日」です。
また「地図の日」にちなんで「最古の日本地図を作ったのは伊能忠敬ではない」「地図の上が北である理由」など地図にまつわる面白い雑学を紹介します。
4月19日は地図の日
今回は「地図の日」について解説していきます!
なぜ4月19日が「地図の日」なのかというと、寛政12(1800)年旧暦閏4月19日に伊能忠敬が蝦夷地の測量に出発した事に由来しています。
普段から当たり前のように使われている日本地図ですが、その日本地図が作り始ための第一歩を踏み出した日だということですね!
この偉大な一歩を踏み出した事から、4月19日は「地図の日」以外にも「最初の一歩の日」ともされています。
もちろん自分の足で歩きまわって日本全国を測量するのですから、とてつもない時間が掛かるのは容易に想像できます。
1800年に始まった測量が終わり「大日本沿海輿地全図」が完成したのは1816年のことでした。
17年もの長い月日をかけた結果、日本史上初めて日本の国土の正確な姿がわかるようになったのでした。
伊能忠敬が亡くなったのは1818年のことでしたので、決して若くはない年齢で全国を測量してまわったことになります。
いかに伊能忠敬が偉大な事を成し遂げたのかがわかりますよね。
地図の雑学
今回は「地図の日」にちなんで「最古の日本地図を作ったのは伊能忠敬ではない」「地図の上が北である理由」など地図にまつわる面白い雑学を紹介します。