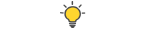この雑学では「八百長」という言葉の意味や語源、由来について解説していきます。
雑学クイズ問題
八百長の名前の由来は?
A.八百万円稼いだ長介
B.八百回勝った長一郎
C.八百日勝ち続けた長十郎
D.八百屋の長兵衛
答えは記事内で解説していますので、ぜひ探しながら読んでみてくださいね!
八百長の意味や語源、由来とは?相撲でよく使われる言葉
スポーツ界の八百長問題
皆さんは普段からスポーツ観戦などを行っていますか?
スポーツに真剣に取り組んでいる選手を見ていると心が熱くなってきますし、選手が真剣に取り組んでいるからこそこちらも応援する気持ちになれますよね。
しかし、そんな真剣に応援している気持ちを裏切る行為として「八百長」と呼ばれるものがあります。
八百長問題は深刻化していて、日本のみならず世界中で問題視されていることから、たびたびニュースで見かけます。
日本では主に相撲などで「八百長問題」という言葉を聞きますが、いったい八百長と相撲にはどのような関係があるのでしょうか。
また、どうして「八百長」という言葉が誕生したかについて、意味以外にも語源由来も含めて解説していきます。
八百長の意味とは?
それではさっそく「八百長」という言葉の意味について解説していきます。
「八百長」という言葉について調べてみると、以下のような意味で使われている言葉だということがわかります。
・真剣に勝負を争うように見せかけて、実は事前に計画、または約束しておいた通りに結末をつけること
・なれあいで事を運ぶこと
一生懸命戦っているように見えても、実際は裏で勝敗を既に決めて行われた出来レースであるため、応援している人にとっては期待を裏切られる行為です。
賄賂や脅しなど様々な理由から八百長は行われますが、如何なる理由でも許してはいけない問題ですね。
八百長の語源・由来とは?
ところで「八百長」は独特な名前をしていますが、何が由来になった言葉か知っていますか?
実は八百長は人名が由来となっており「八百屋の長兵衛」の略だったのです。
明治時代に八百屋の店主をしていた長兵衛は囲碁仲間である大相撲の伊勢ノ海と碁を打つ際に、伊勢ノ海の機嫌を取る為にわざと負けていたという話から来ています。
このことから、わざと負けることを八百長と呼び、様々な勝負事でも使われるようになりました。
長兵衛の八百長が発覚したのは、囲碁の棋士である本因坊秀元と互角に勝負をしていたことがきっかけです。
囲碁の実力が優れていた長兵衛だったからこそ、相手に合わせてわざと負けるということも出来たのかもしれません。
また八百長は「八百屋の長兵衛」ではなく、「八百屋で水茶屋を営んでいた斎藤長吉」という説もあります。
長吉説は1901年に朝日新聞が書いた物とされていますが、どちらが正しいのかは分かっていません。
以上が八百長という言葉の意味や語源由来についてでした、いかがでしたか?
注目記事
それでは雑学クイズの正解発表です、答えはもうお分かりですよね?
雑学クイズ問題解答
雑学クイズ問題の答えは「D.八百屋の長兵衛」でした!
この問題以外にも、思わず人前で披露したくなる楽しい雑学クイズ問題を用意しています。
全て解けたら雑学王かも!?
【目指せ雑学王】面白い雑学クイズ問題集!【解説付き】
他にも、こんな雑学がお勧めです。
檄を飛ばすの意味と語源、70%以上の人が間違えてます。
野球は昔、21点先取制ルールだった!?
人口が5人しかいない国、ワイ公国とは!?
まとめ
八百長は、真剣勝負を装い事前に勝敗を決めておくこと、という意味がある。
「八百屋の長兵衛」が囲碁の勝負にわざと負けたことが由来している。
別の説では「八百屋の長兵衛」ではなく「八百屋で水茶屋を営んでいた斎藤長吉」という説もある。